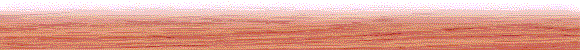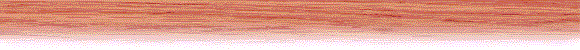
書籍など 特集
ニュースのトップへ
このページは、「Oct.14thのホームページ」の一部です。
Internet Explorer の文字サイズを「小」にすると見やすいです。
( 「表示」→「文字のサイズ」→「小」 )
サッカーワールドカップ南アフリカ大会まであと1週間を切りました。 と言うことで、今日はサッカー特集です。 ○サッカー日本代表 システム進化論 最近の日本代表ですが、W杯を前にしてボロボロですね。 なんで監督を変えないのかがわかりません。 こんなに勝てない監督がクビにならない国なんて無いんじゃないの? ということで、今日は「サッカー日本代表 システム進化論」と言う本の紹介です。 サッカーのシステムに関しては、このページのちょっと下のほう('09.5.17)で 「4-2-3-1 サッカーを戦術から理解する」 を紹介しています。 こちらは世界のチームを例に出してシステムをわかりやすく紹介しているのに対し 今回の「サッカー日本代表 システム進化論」は その名の通り日本代表に関するシステムの歴史の本です。 私としてはファルカンの解説が少ないのが不満ですが 日本代表の歴史を知るには非常に良い本だと思いました。 W杯前に2冊一緒に読むと、もっとW杯を楽しめると思います。 ちなみに、こないだのコートジボワールとの親善試合前に 後輩のウォヴィータと 「ドログバのプレー見たいよね」 って話してたのに・・・速攻でいなくなりました。 しかも、W杯も絶望かも。 T莉王なにやってんねん!! 日本のオウンゴールなんかより こっちの方がよっぽど世界的に大問題だよ!! 我らがFC東京の今野も膝を怪我したし・・・ 最悪です。 |
○禅林寺(森鴎外、太宰治 墓所) 5月22日(土)の朝、禅林寺にある 森鴎外、太宰治のお墓を見に行きました。 当初は禅林寺に行くつもりは全くなく ただ単に、この近くに用事があって出かけました。 この日は天気もよく、少し時間も空いたので 時間つぶしに禅林寺のお隣にある「八幡大神社」でお参りをしました。 八幡大神社 とにかく日差しと緑が気持ち良い朝でした。 そして、ふと、そーいえば、隣は禅林寺だなぁ 三鷹に移り住んではや10年。 毎日毎日、晴れの日も雨の日も 禅林寺の正面、および横の道を歩いて通勤しているのにも関わらず 禅林寺にあると言う、森鴎外と太宰治のお墓は一度も見たことがないなぁ と言うことで、とりあえず禅林寺に入ってみました。 (一般人が入れるのかも知らずに) これが門です。 工事関係の人と、お掃除をしている人が数人。 一般人は俺と長女だけっぽい。なんか入り辛い。 ・・・っていうか入っていいのかな? 恐る恐る入っていくと、少し奥に看板発見。 ●墓参時間 午前8時 → 日没 日没以降は外に出られなくなりますので特にご注意ください。 墓参以外は立入禁止 と言う文章と共に、地図が描いてあります。 門の付いた細い通路だけが、お墓への唯一の通路みたいです。 その細い通路で掃除しているおじさんの横を 恐る恐る通りながらお墓へ抜ける通路を歩いて行きました。 比較的こぢんまりとしたお墓をずっと奥に入って行くと・・・ どうやら目的地へは一筋間違えた模様。 「あれ? パパ一筋まちがえちゃったかな?」 って話してたら、一般のお墓参りに来ていたおっちゃんが 「なに? 見学? そこ、森林太郎(鴎外)・・・・で、そっちが太宰治 そっちの道からぐるっと回れるから」 って親切に教えてくれました。 一般のお墓参りの方は、このおっちゃん以外に初老の夫婦が一組だけでした。 写真 左) 太宰 治 写真 右) 森 林太郎(鴎外) お花も線香もありませんでしたが(ふざけてる!) とりあえず手を合わせてお参りいたしました。 写真 左) 右に森、左に太宰のお墓、真ん中に長女。 写真 右) 門の近くに、森鴎外の遺言の石碑がありました。 土曜の良く晴れた午前中だったので、お墓と言えど凄く気持ちがよかったです。 これが雨のそぼ降る夕方だったら結構怖かったかも。 このお墓参りでわかったこと。 俺、二人のお墓から直線距離にして20〜30メートルほどのところを 毎日歩いて通勤しておりました。 |
先日62歳で退職された上司 (長らく私とコンビを組んでいました) が大変な読書家でして その上司が本を読み終わると、その読み終わった本を私の机にポンポン投げていくんですよ。 ハードカバー、文庫、雑誌など。 また、そのジャンルもバラバラです。 別に「読め」と言うわけでもなく「読まないなら捨てて良いぞ」とも言いません。 朝、会社に出社すると机の上に本が置いてあります。 私としては 「もらえる物は全てもらいます」 って感じで、それらの本を読んでいます。 今日はその中の一冊を紹介します。 ○「輝ける闇」 開高 健 「輝ける闇」 一応わたくし、この開高健さんの顔は知っております。 少し太ってて、メガネかけてて、タバコ吸ってて、魚釣ってて、お酒飲んでるおっさんでしょ? しかも開高健の「健」は「けん」ではなく「たけし」だと言うことも存じ上げております。 ・・・・が、知っているのはココまでです。この人がどんな作品を書いたのか また、どんな人生を送ったのかは全く知りませんでした。 そんな折り、私の机に 「輝ける闇」 開高健 が投げられていました。 なんじゃこれ? と思って本の背表紙を見ると 「ヴェトナムの戦いを肌で感じた著者が、 生の異相を果敢に凝視し戦争の絶望とみにくさをえぐり出した書下ろし長編」 と書かれています。 「げっ! このおっさんあの体型(体型は関係ないか?)でベトナム戦争に行ってんの?」 かなり驚きました。(少し上の世代の人には常識でしょうが) 本当に何の基礎知識もなく 「面白いんか、この本?」と思いながら読んでみたんですが めちゃめちゃ良いです。 この内容で540円は安すぎます。 私の世代で「ベトナム戦争」と言えば 「枯葉剤」 「ダイオキシン」 「ベトちゃんドクちゃん」の他は 「プラトーン」 「ランボー」 「グッドモーニングベトナム」 「7月4日に生まれて」 「フォレスト・ガンプ/一期一会」 などの 「アメリカ人から見た『ベトナム戦争』」 しか知りませんでしたが この本は 「日本人が見た『ベトナム戦争』」です。 アメリカ人の作った「ベトナム戦争映画」と違って 「偽善」や「ヒーロー」や「盛り上がり」や「ハッピーエンド」やはどこにも有りません。 ただ淡々とお話が進むだけですが、迫力と説得力は桁違いにあります。 アメリカ人には理解できないであろう「感動」が、この本には有るような気がします。 みなさんも一度読んでみて下さい。 この「輝ける闇」が私の机に投げられた数日後 「ベトナム戦記」が投げられていました。 こちらはまだ読んでいませんが、楽しみですね。 |
毎日、通勤電車の中ではたいてい読書をしております。 往復で一時間ちょっとでしょうか。 月の前半は、とある月刊雑誌(毎月1日発売)を読んでいますので 月の後半を使ってその他、諸々の分野の本を読んでおります。 こないだ、ここ一年半くらいの間に読んだ本をまとめてみましたら、約40冊になりました。 月の半部を使っているので、実際は9ヶ月くらいの間に40冊! え!? マジ? 俺ってこなんなに読んでんの? 自分でもビックリです。 と、言うことで、今日は本の紹介です。 ○「悩む力」 姜 尚中 (カン・サンジュン) 「悩む力」 結構前からずっと本屋の一押しで並んでいます。 姜(カン)さんが書いた本です。 姜さんって最近テレビに良く出てまして、冷静でダンディーで優しい語り口調が特徴的な おばさま達に絶大な人気を誇る政治学者です。 他のテレビに出ている教授達と違い、静かに語りかけるような口調で 重みと説得力が有って凄く好きなんですが、どうもテレビに出ている人が書く本って 「面白くない」っていう先入観がありまして、なかなか読もうとは思いませんでした。 しかしこの本、あまりにも長い間本屋に置かれているので 「根負けした」って感じで、手に取り、買ってしまいました。 本の内容はあまり詳しく書きませんが、読んでいる間、終始あの静かな口調で 淡々と語りかけられているような感じがします。 思ったより面白く、なんと言っても最終章「老いて『最強』たれ」で 姜さん本人が今後の目標というか意思表明みたいな事を書いています。 この部分を読むと 「このおっさん、見た目によらずめっちゃ面白い! 冷静な語り口調の裏に熱く燃えたぎるお茶目な情熱を持っている!」 って思いますよ。 世のおばさまだけでなく、30代半ばのサラリーマンの心も鷲掴みにしやがりました。 完全にやられました。 姜さん、人間として魅力的です。 |
○太宰 治 (玉鹿石 太宰を偲ぶ無銘碑 +楳図かずお) 2009年6月19日は太宰治の生誕100年でしたね。 玉川上水で遺体が発見されたのも6月19日だったそうです。 別に私は熱狂的な太宰ファンではありまでんが 一応、「人間失格」「斜陽」あたりは読んでいます。 しかしながら、ずいぶん前に読んでいますので 読んだ記憶は有るんですが・・・内容は覚えてナイヨウ・・・・(失礼) 三鷹市は太宰治の第二の故郷であり 数多くの作品を生んだ土地であり、そして亡くなった土地であります。 一応さ、三鷹市民の私としては、太宰治が入水自殺したあたりに 人知れず置いてある「玉鹿石」って言うものの存在を知っているわけですよ。 あの超有名で熱狂的なファンが多い「太宰治」を偲んでいるにもかかわらず 太宰の「だ」の字も書いてない! なんと言っても、あまりにも目立たなさすぎ! 知らない人にはただの普通の石であり 何のために置いてある石だか全くわからないと思います。 ファンが探そうとしてもなかなか見つからないとも聞きます。 あまりにも呆気ない寂しいモニュメントなので はじめは「可哀想」と思ったんですが 今は、それを通り越して 「さすが太宰治! イメージにぴったり!」 って思います。 皆さんも探してみてね。 ↑ 2009年6月20日(土)の午前中に通った時の写真です。 左側に紫陽花が置いてありました。 何度も見ているのですが、お花が手向けてあるのは初めて見ました。 さすが、「太宰治 生誕100年」・・・・・って思ったんですが すぐ横のマンションの植え込みに、同じ紫陽花が沢山咲いていました。 なんだよ! わざわざ花屋で紫陽花を買ってきたんじゃなくて 3m横の植え込みからパクったのかよ! ちなみに、この写真を撮った直後 三鷹方面から、いつも通りの赤い服を着た「楳図かずお」さんが ひょこひょこと井の頭公園方面へ向かって歩いて行きました。 この通りで見たのは初めてです。 太宰治 + 楳図かずお とってもミラクルなコラボでした。 |
○4−2−3−1 サッカーを戦術から理解する 最近はサッカーネタが多いので、今回はサッカーに関する書籍を紹介します。 今回は「4-2-3-1 サッカーを戦術から理解する」 著 杉山茂樹 光文社新書 です。 1年ほど前に、本屋にめちゃめちゃたくさん列んでいたので 読まれた方もいるかと思います。 ------------------------------------------------------- この本に関しましてネットで検索いたしますと 知ったぶった人達によって 「サッカーは、こんな単純なものではない」 とか 「反例はたくさんある」 とか書かれていますが 私の意見は、「この本は、もの凄く面白い」です。 とりあえず、「フォーバック」 「スリーバック」 「トップ下」 「4-4-2」「3-4-1-2」とか、知ってはいるけど詳細までは・・・ と言う人には凄く解りやすくこれらの事を解説していますし もう少し知っている人にも、もっと理解出来るように書かれています。 さらには、 「なんで日本代表って点が入りそうで入らないんだろう?」 「なんでジーコ・ジャパンって勝てなかったんだろう?」 「なぜ、お隣のヒディング韓国は勝てたんだろう?」 と言う疑問にも答えてくれます。 ------------------------------------------------------- 私個人的には、オフト(ヴェルディー=日本代表)から トルシエまでの「時代遅れのサッカー」や ジーコ・ジャパン時代に、「黄金のカルテット」と称して N田、N村、O野、I本をボックス型に配置する間違った戦術などを 堂々と批判してくれる点も嬉しくてたまりません。 あんなんじゃ、勝てるわけありません。 さらに、私の意見を言わせて頂くと、 ジーコ・ジャパン以降の日本代表のように 「N村S輔のようなプレースタイルの選手」が 日本代表の中心となっている限り 日本代表はアジアで勝てても世界では勝てないと思います。 (N村選手自体が悪いんじゃないですよ!) ------------------------------------------------------- それと、皆さん、94年のファルカン・ジャパンって覚えています? オフト監督の次の監督で、半年くらいでクビになりました。 結果としては、ジーコと同じ様なブラジルサッカーを目指していたので 多分、そのまま続けていてもジーコ・ジャパンのような失敗をしていたと思いますが、 当時、全く納得のいかなかったオフト・ジャパン(ラモスとヴェルディーの選手が仕切っていた)から 心機一転し、やっと人気や露出度によらず、本当に実力の有る選手によって 日本代表のサッカーも世界のサッカーに近づくと思ったんですが・・・ 当時のマスコミやサッカーを知らない人達によって潰されました。 もしファルカンが続けていてくれたら・・・・ 2006年のジーコの失敗が10年以上早くわかったことになったのに・・・ ファルカンを辞めさせたことによって、日本代表は10年以上、遠回りをしています。 残念です。 ------------------------------------------------------- まあ、このように、サッカーの話題は人それぞれ、話し出すと尽きないものです。 これらの「話のネタの提供」としては、この本は最高の本です。 この本の内容や、今の日本代表、世界のサッカー、 そして各個人が勝手に日本代表の監督になって それぞれが描き出すサッカーに関して お酒など飲みながら話し合うのは最高に楽しいと思います。 是非、皆さん、この本を読んで私と朝まで語り合いましょう! ------------------------------------------------------- え〜、ちなみに私が好きなスタイルは、イングランドの伝統的な4−4−2です。 二番目の「4」が横一列に並ぶやつね。 FC東京がそれっぽいシステムを採用しているんだけど 如何せん、攻めこまれると、中盤の「4」がズルズル下がりだして・・・ バックの「4」に吸収されだして・・・中盤が薄くなって・・・ 中盤でのプレスが全く効かなくなりはじめて・・・ 相手にボールをコントロールされて・・・ さらにサイドから崩されて・・・ クロスをあげられるとなぜかマークが外れまくってて・・・ キーパーもレベル高くないし・・・あっと言う間に失点へと・・・・ いかん! このページでも語り出すと止まらねー!! |
○ゾウの時間 ネズミの時間 前回のニュースでも書きましたが、このHPを始めてから10年の月日が経ちました。 最近、特に一年がとても早く過ぎ去るような気がします。 それに比べて子供の頃の一年ってすごく長かったようか気がしません? その疑問に答えてくれる本がこの一冊です。 「ゾウの時間 ネズミの時間」 東工大の本川達雄教授が書いていて、1992年に出版された本です。 ----------------------------------------------------- 1.なぜ大人の一年は短く感じるのか? この本全体をめちゃめちゃ大雑把に要約いたしますと ○生物のあらゆる事柄は、その生物の体重Wによる 意外と簡単な関数で表すことができちゃいますよ ってことです。 さらに、さらに、この本の中心となる内容は 生物の時間は、体重Wの1/4乗に比例する 時間 ∝ (体重)1/4 ってことです。 体重が16倍になると、時間は(16)1/4 = 2倍になるっていう計算です。 この時間は、寿命も呼吸も心拍も、あらゆる時間に掛かってくるそうです。 これを言い換えると 体重の軽いネズミは「呼吸」も「心拍」もゾウより早く、寿命もゾウよりずっと短い。 ゾウは呼吸も心拍もすごくゆっくりで、寿命も長い。 けど、ネズミもゾウも、どちらも一生のうちに行う 「呼吸」や「心拍」の数は同じってことです。 小さい動物ほど、全ての時間が早く流れ、 大きい動物ほど、全ての時間がゆっくり流れるそうです。 けど、やることの「数」は同じってこと。 だからね、いわゆる人間の言う「一年」の間に ネズミは人間よりすごくたくさんの時間を生きているわけですね。 心臓もたくさんドキドキしているし、呼吸もたくさんしているし 餌もたくさん食べてるし、成長もたくさんしています。 上式から計算しますと、体重60kgの人間時間の「1年」は 体重100gのネズミにとっては「5年」に相当します。 逆に、体重5トンのゾウにとっては「4ヶ月」分にしかなりません。 ちなみに20kgの子供にとっては、「1年4ヶ月」に相当します。 つまりですね 体重の軽い(20kg)子供のころの「1年」は 体重の重い(60kg)大人になってからの「1年」よりも 4ヶ月分長かったんですね。 ----------------------------------------------------- 2.俺の説です ちなみに俺の説は 上述しためんどくさい理論なんか関係なく 単純に自分の生きた年数を基準(分母)に1年を考えるから 1年が短く感じるだけだと思います。 18歳の時の1年は 1/18 35歳の時の1年は 1/35 歳を取ったほうが1年は短く感じます。 ----------------------------------------------------- 3.本当に短く感じる? それともう一つ 確かに1年は短く感じるのですが 3年の感覚は昔と変わらず3年に感じます。 なぜだろう? 次女が生まれてから、もう少しで3年ですが 感覚的には5年くらい一緒に生きてる気がします。 長女なんてまだ5歳なのに、10年くらい一緒にいるような気がします。 なぜだ?! 教えてくれよ、本川教授!!!! ----------------------------------------------------- 4.本を読んだ感想 と、ここまで書いておいて、この本を読んだ「批判的な」感想ですが・・・・ 学術的、研究的には 「本当かよ? ちょっと強引じゃね?」 「例外はたくさん有るでしょ?」 って思います。 ------------------------------------------------------------- 5.結言 しかし、この本、雑学的には 「おもしれーじゃん」 「飲み会のネタに十分使えるじゃん」 「珊瑚会のネタとしては最高ですな」 って感じです。 話のネタに一度は読んでみる価値はあると思います。 上述した時間の事以外にも、以下のような面白い話がたくさん載っています。 ・動物の進化のお話 ・島の規則 ・ゾウの足は折れて当たり前のお話 ・なぜ移動手段に「足」よりも遙かに効率の良い「車輪」を持った生物がいないのか? ・なぜ飛ぶ手段に「プロペラ」を持った生物がいないのか? ・昆虫、珊瑚、棘皮動物の不思議なお話 などなど、この本さえ押さえておけば 君も合コンでモテモテです! 注意) 生物学科卒業の女性には使用しないで下さい! |
○奇跡の寝相(その7) お盆休みの時ですが、私が読んでいた小説「四つの嘘」(大石静)を ゴロゴロ寝ながら読んでいました。 親のヤラセではありません。本を取り上げようとすると「マジ切れ」します。 まともに喋れもしないのに、どうやって文字だらけの本を理解しているんでしょうか? 本当にこの「アラフォー女」の微妙な心の動きを理解しているのでしょうか??この二歳児がぁ・・・?? それとも将来は「永作博美」にでもなるつもりなんでしょうか? ↑ 「なに撮っとんじゃボケッ!」と、指をさしながらカメラマンにガンを飛ばします。 ちなみに「四つの嘘」はテレビ朝日系列で「ドラマにもなりましたよね。 珍しく、本よりドラマのほうが面白かったです。 |
○夕凪の街 桜の国 先日、私の隣に座っているM田さんが 「これ知ってる?」 と言って差し出したDVDが 「夕凪の街 桜の国」でした。 M田さん曰く、ヒロシマの原爆のお話らしく M田さん : 「何も知らずに借りて見てみたら、涙が1リットルくらい出たよ。」 とのことでした。 M田さんと言えば、私の勝手なイメージでは、「武闘派」で 「原爆? もっと落とせば?」 って言うようなイメージ(←すみません、勝手な偏見です)があるんですが・・・ 「涙が1リットル」 と言われて少し驚きました。 さっそく、ネットで調べました結果 どうやら原作は「マンガ」らしいことがわりました。 しかも、数多くのサイトで話題になっていて その評価たるや、絶賛の嵐です! その日の会社帰りに、吉祥寺の本屋で原作のマンガを買って帰りました。 思ったよりペラペラな本でして え!?こんな薄っぺらいの?って感じです。 家に帰って読みました・・・ 一回目読んで・・・ ん〜 巻末の「解説」と「あとがき」を読みました。 そして2回目を読んで・・・ ん〜 深いな〜 このマンガは 「絶賛の嵐」状態がわかる気がする。 深い。 たった100ページにも満たないマンガなのに・・・深いです。 さらに先週末には、DVDを借りて映画版を見ました。 凄いですね。 マンガよりわかりやすく、面白いです。 とてもよく出来た映画です。 基本的に原作に忠実に作っていますが 原作がしっかりしているので、映画も良いです。 と言うか、原作以上に良いです。 最近見た映画ではNo.1です。 (最近めっきり映画を見ていませんが・・・) ストーリーはもちろん、映像も綺麗で良いですよ。 「夕凪の街 桜の国」に関しまして ストーリーや内容は、敢えてココには書きません! でも、一つ一つの台詞や、登場人物の考え方が・・・深いです。 皆さんもDVDを借りて見ましょう! 涙が1リットル出るかも! ------------------------------------------------------------------ 余談−1 「夕凪の街 桜の国」の中で 春日八郎の「お富さん」(←曲が流れるよ)が出てきます。 「死んだは〜ずだ〜よ おとみ〜さん〜」ってやつですね。 映画でコレを聞くと 「男はつらいよ」でおなじみの 山田洋次監督の「息子」を思い出します。 三國連太郎と永瀬正敏が親子役で、和久井映見も出演している1991年の映画です。 この映画でも、「お富さん」の歌が効果的に使われています。 ------------------------------------------------------------------ 余談−2 原爆の映画と言えば、長崎を舞台とした 巨匠、黒澤明監督の「八月の狂詩曲」〜八月のラプソディー〜を思い出します。 この映画も1991年の映画で、リチャード・ギアも出演しています。 ここで問題です。 「八月の狂詩曲」にも「夕凪の街 桜の国」にも出ている俳優さんがいます。 さて、誰でしょう! ------------------------------------------------------------------ 余談−3 この「夕凪の街 桜の国」 「息子」 「八月の狂詩曲」 「お富さん」 に関しまして 「映画を語らせたら、木更津では右に出る者はいない!」 と言われた 我らが「はまつぁん」に、感想および評価を聞いてみたいです。 と言うことで、我らが「はまつぁん」 お願いいたします。 |
○五木寛之 先週、仕事で五木寛之氏の講演「今を生きる力」を聞きました。 私の仕事に関係する、とある団体が主催した講演会です。 この講演の案内が来た瞬間 「うぉー! 五木寛之やんけー! ・・・でも、なぜこの業界で五木寛之???」 と思ったと同時に この業界の講演会で、五木寛之と言う人物を選んだ人を凄いと思いました。 ------------------------------------------------------------- 講演の内容は、大体以下の通り(順不同) ・世の中には「慈-悲」「陽-陰」「躁-鬱」など裏表の関係がある。 ・表裏の関係は必ず両方必要である。片方だけじゃダメ! ・嬉しいときは嬉しがりなさい。 ・「笑う」ことが人間の心と体に良い影響を与えることはよく知られている。 ・最近の研究で、「悲しむ」ことが「笑う」ことと同様に、人間の心と体にとても良い影響を与えることがわかった。 ・悲しいときは周りに向かって「悲しい!」と宣言し、泣いて悲しみなさい。 ・人間にとって悲しい時に「悲しむ」のは必要な行為です。 ・戦後は貧しかったが、国民全体に希望があった。 ・全てがどん底だったので良くなるしかない時代だった。 ・それから50年、高度経済成長や東京オリンピック、大阪万博、長島巨人など、全ての分野で「躁」の時代が続いた ・これは異常だ! ・その後、時代は「鬱」の時代に入り、ココ10年は、全ての分野が世界的に「鬱」状態である。 ・近年、自殺者が増えている。 ・年間3万人と言うデータがあるが、遺族が「事故死」とする場合が多く、実際はそれの数倍はある。 ・精神科に行く程ではない軽い「鬱」状態の若者が、臨床内科にかかり、薬をもらって治療している。 ・これには反対である。 ・「鬱」は本来必要である。 ・人間は風邪をひく。コレは体の自浄作用であり、風邪をひくたびに体が綺麗になる。 ・風邪くらいひかなくてどうする! ・人間、「鬱」くらいならなくてどうする! ・「鬱」と言う漢字は本来、「鬱蒼とする」など、エネルギーが充ち満ちた状態のことを指す漢字である。 ・エネルギーが覆い被されて、充分に表に出せない「鬱々」とした状態が「鬱」である。 ・「鬱」は心が萎えている状態である。 ・心が萎えて、次なる飛躍に向かって準備している状態である。心の自浄作用である。 ・冬の兼六園では、木々の枝が雪の重さで折れないように「雪吊り」をする。 ・プロの職人が折れそうな枝を選び、上から枝を吊る。 ・どのような枝を選ぶかと言うと・・・「堅い枝」を選ぶ。 ・弱くて萎える枝は、雪が被っても、「萎え」て「しなる」から折れない。 ・一見強くて堅い枝は、雪の重さで「ポキッ」と折れる。 ・人間も同じである。 ・強い人ほど、折れる。 ・「弱く」「鬱」になり、「萎え」、「悲しむ」人間は、最終的には折れない。 ・「萎え」、「しなり」、「耐え」て春を待つ。春が来たら立派に元に戻る。 ・だから、「鬱」状態は必要であり、次なる飛躍への準備である。 ------------------------------------------------------------- 大体、以上の通り。 私が文章に書くと「陳腐」なものに聞こえますが 五木氏が語ると、さすがにプロですね、 話し方がとても上手で、お話に引き込まれずにいられませんでした。 後から関係者の方に、講演料を内緒で教えてもらいました。 「えー! 2時間でそんなに取んの!」 と思いましたが、今考え直してみると、その価値は有ると思います。 |
○読書に関する見解 このHPにも時々書籍の話題を載せていますが 私は平均な人よりは、活字を多く読んでいるほうだと思います。 (一応、私の「職業」および「年齢」を考慮にいれて下さい。) 本のジャンルは多種多様です。 私の読書歴を紹介いたしますと とりあえずスタートは、皆さんと同様かと思われますが 「マンガ」 からスタートしています。 小学校低学年の頃の「コロコロコミック」からはじまり 大学生時代の「モーニング」あたりまででしょうか。 大半の少年誌から少女マンガまで読んでいます。 実際、私の実家には数千冊のマンガ(単行本)があります。 「全てのマンガを読んだ!」 とは言いませんが 「全てのパターンを読んだ!」 とは言えるような気がします。 例えばこのHPを読んでいる加齢臭くさい「ドカタ」野郎達の中で 「ホットロード」「あさきゆめみし」「はいからさんが通る」「ときめきトゥナイト」 などの少女マンガまで読んだことがある人は意外と少ないと思います。 とにかく、日本のマンガは世界に誇る「文化」だと思いますし 私もマンガから大変多くのことを学びました。 「友情」「勇気」「根性」「人生」「恋愛」など あと「ビジネス」も学びましたかね。 ・・・「ビジネス」で思い出したけど 「課長 島耕作」ってスタート時点で確か33歳で 第1話か第2話くらいで34歳になり さらには34歳で「初芝電器」の営業系の「課長」になっているはずです。 (単行本は実家にあるので、ココでは正確な確認ができませんが・・・) 34歳で「課長」ですぜ しかも我が社のように名前だけの「課長」じゃなくて 名実共に「一つの課」を任されている「課長」です。 さすがに後に「社長」になる男は違います。 ・・・・・・・話がそれましたので戻します。 マンガから卒業したのは大学に入ってからでしょうか。 その理由は(かなり傲慢な意見ですが) 「すでにマンガから学ぶべきものは何も無い!」 と悟ったからです。 それ以降、そこそこ本を読んでいます。 本のおもしろさ、奥深さ、その情報の質と量は、マンガの比ではないと思います。 極端な意見ですが 「本を読まない人間は人生を損している」 とまで思います。 皆さんも騙されたと思って本を読んでみましょう。 ちなみに、とある有名な女性の書いた本の中で 「本の値段換算で1万円分に一冊、非常に良い本がある」 と書いてありました。 つまり、5千円の本なら2冊に1冊 500円の本なら20冊に1冊、良い本があるそうです。 本の世界も「安かろう悪かろう」が成り立つみたいですね。 |
○書籍紹介 と言うことで、本日は一冊の本を紹介したいと思います。 その本は 「3年で辞めた若者はどこへ行ったのか−アウトサイダーの時代」 です。 今年の3月、ふらふらと本屋を歩いていたところ 新書のコーナーに置いてあるこの本が目にとまりました。 私も既に入社10年以上経ち、数多くの先輩、同期、後輩が会社を辞めて行きました。 そして、ふと 「・・・・・そう言えば、会社を辞めていった多くの仲間達は、 一体全体、今、どこに行って何をやっているのだろうか?」 と言う疑問が沸き立ち、この本を買ってしまいました。 既にこの本を読んでから数ヶ月が過ぎているため、 正確な内容は覚えていませんが、あえて感想を書かせて頂きます。 (ココに書くために、読み直したりしていません。ちょっと違っていても勘弁して下さい。) 内容は、私たちと同世代、もしくはそれより若い世代の人で 新卒で就職した会社を辞め、あえてアウトサイダーの人生を 選んだ人達がたくさん紹介されています。 たいへんおもしろく、あっと言う間に読んでしまいました。 やっぱり凄いヤツはいるもんだなぁーと関心しました。 この本を読んで分かったことは以下の2点です。 ・なぜうちの会社には、あまり学生が就職してこないのか ・自分自身、昭和の価値観の中で生きている最後の世代であり お先真っ暗な最悪の世代であること こんなとこでしょうか・・・・ 最後のほうは、作者の意見がズラズラっと書かれています。 少々偏った意見もありましたが、世の中こんな考え方もあるのかぁー と関心してしまいました。 みなさんも一度読んでみて下さい。 それにしても、20代の一時期、私達とバカなことばかりやって 楽しく過ごした「仲間」達は、今どうしているのでしょう? おーい!みんな元気か? |
○上田城千本桜まつり 4月13日、信州の上田城に桜を見に行ってきました。 現在、上田城では、「上田城千本桜まつり」をやっています。 ○上田城と歴史小説 上田城と言えば、真田昌幸、信之、幸村父子で有名でして なんと言っても、徳川軍を二度も撃退している城として お城ファンの間ではめちゃめちゃ人気の高いお城です。 NHKの番組で行ったお城ファンが選んだ「好きな城ベスト10」でも堂々の1位を獲得しています! 私自身、「真田太平記(全12巻)」(池波正太郎) 「関ヶ原」 「城塞」 「覇王の家」(司馬遼太郎) など、数多くの歴史小説を読破している 「隠れ歴史小説ファン」 の私としては生唾もののお城です。 ちなみに、こないだ仕事で行った「函館」では 「うぉー! ここが 『バラガキのトシ』が流れ流れてやって来た地かー!」 と、ちょっと興奮していました。 しかしながら、時間が無くて、観光は全くできませんでした。 詳細は 「燃えよ剣」(司馬遼太郎)を参照して下さい。 司馬遼太郎の小説の中でも、最高傑作だと思います。 とりあえずこの小説を読んで、小説内の土方歳三のファンにならない人はいないと思います。 特に私は、今現在住んでいる地域がふんだんに小説内に出てくるので思い入れも強いです。 歴史小説に関しては、別の機会にゆっくり語りたいと思います。 |
○いわむらかずお もう一ヶ月以上前の話しになるんですけど、吉祥寺の伊勢丹(新館7F)にある武蔵野市立吉祥寺美術館に「いわむらかずおの世界」と言う展示を見に行きました。 「いわむらかずお」って言われても良くわからないんですけど、とりあえず娘が持っている「ねずみのさかなつり」って言う絵本を描いた人です。つまり絵本作家です。 この「いわむらかずお」さんって、正直絵本で見る分には 「たいしたことねーなぁ」 って思ってたんですけど(すみません)、やっぱ本物は違いますね。めちゃめちゃ綺麗だし、人間の成せる業じゃないです。鳥肌が立つほど凄いです。 帰り際に、美術館で販売していた「14ひきの あきまつり」を買って帰ったんですけど、やっぱり絵本になると絵の良さが半減してしまいますね。残念です。 ちなみに娘のほうはと申しますと、興味を持ったのは一瞬で、すぐに飽きてしまい 「もう帰る。」 の連発でした。さすがに俺の娘だけあるなぁ。「休日は美術館」って言うガラじゃないんでしょうね。 |
○戦場のメリークリスマス こないだ超久しぶりに見ました。「戦メリ」こと「戦場のメリークリスマス」 年末に実家に帰った時に兄貴からDVDをもらったんですが、何せ最後に「戦メリ」を見たのが多分15年以上前だから、ほとんど内容を覚えていない! 思い出せるのは、私が通っていた小学校の掃除の時間のBGMとして使われていた曲 「Merry Christmas Mr.Lawrence」と、一番最後のシーンの5秒間だけです。 いつも通り子供を寝かしつけた後に、女房と一緒に映画を見たんですが、 「あー、あったあった、こーゆーシーン!」 「そうそう、こーゆーストーリーだったわ!」 と全て後付で思い出すだけでした。 感想はと言いますと・・・ ちんたら、ちんたらと続く「生ぬるいストーリー」のせいで少々睡魔に襲われつつ 「やっぱ『戦メリ』って長げーなー」と飽きも出つつ・・・ でも結局のところは・・・ 世界に通用する俳優さんの有名なラストシーン(台詞)と、 それに続きます世界に通用する作曲家の 「ちゃららららん〜 ちゃん ちゃららら ちゃららららん〜」 の曲のせいで、 「あ〜やっぱ『戦メリ』って良い映画だよな〜」 って感じちゃう自分がむかつくよね。 終わり良ければ全て良しって感じです。 みんなもそう思わない? |
○灰谷健次郎 06.8.25のニュースで書きました作家の灰谷健次郎さんが11月23日に食道癌のため72歳で亡くなりましたね。ニュースでも取り上げられていましたし、新聞にも大きく載っていました。今日はNHKで過去に出演した番組を再放送していました。 やっぱり結構有名な人だったんですね。ご冥福をお祈りいたします。 |
○嫌われ松子の一生 なんか最近、「嫌われ松子の一生」がドラマ化されるみたいですね。この「嫌われ松子の一生」は、沖縄-羽田間の飛行機内で読みました。 前にも少し書きましたが、沖縄の「おろじゃす」(沖縄ジャスコ小禄店)の中にある本屋で「兎の眼」「太陽の子」や重松清の本を買っていた頃、ちょうど映画化された時期で、たくさん宣伝されていたので、思わず「嫌われ松子の一生(上・下)」を買って読んでしまいました。 お話のほうは?と言いますと、エンターテインメント的にはすごく面白いですし、これはこれで有りだろって感じです。でも、こんな内容のお話をどうやって映画化したんだろう・・・?と心配にもなりました。 主人公に対して真剣に感想を書けと言われましたら、「確かにアンラッキーな所も有るけど、基本的には自業自得だな。本当にこーゆー人間がいたとしたら、死ななきゃ治んないだろうなぁ。」って感じです。あまり同情はできません。こんなこと書くと敵が増えそうですけどね。 |
沖縄勤務中、2〜3週間に一度は東京や女房の実家に帰っていたので、移動中の飛行機や新幹線の中で結構本を読みました。今日はその読んだ本の紹介です。 ○灰谷健次郎 フットサルチームで俺と無敵のツートップを組む先輩に 「この本結構おもしろいから読んでみな」 と言われて渡されたのが、灰谷健次郎さんの「いま、島で」でした。 内容は、淡路島で自給自足生活をしながら生活する作者のエッセイ的な本で、昭和59年に出版された本でした。 その時の印象としては 「癖のあるおじさんだけど、おもしろいと言えばおもしろいか・・・」 という程度でした。 さらに灰谷健次郎さんを調べてみますと 知らないのは俺だけ? 大変有名な方でして、代表作には 「兎の眼(1974年)」 「太陽の子(1978年)」 などがあり、ドラマ化や映画化されたりと、大変有名な方と言うことがわかりました。 また、小学校低学年の国語の教科書に載っていた 「ろくべえまってろよ」 もこの人の作品らしいですね。 と言うことで、沖縄の「おろじゃす」(沖縄ジャスコ小禄店)の中にある本屋で「兎の眼」「太陽の子」を購入して読んでみました。 -------------------------------------------- 「兎の眼」 「兎の眼」は、元国語教師である作者の経験談なのかどうかはわかりませんが、あまり裕福でない家の子供たちと新米女性教師のお話でした。 ・・・と書いてたら、学生自体に読んだ「二十四の瞳」を思い出してしまいました。 結構同じ路線かもしれません。 この本もさらりと読めるし非常に良い本でした。 -------------------------------------------- 「太陽の子」 そして、そして「太陽の子」は沖縄に関するお話でしたが、羽田-沖縄線の機内で沖縄の話しを読むというのはなかなか「おつ」なもんでしたし、お話にでてくる沖縄口(ウチナーグチ(沖縄の方言))や郷土料理が、実際に解るというのは非常にお話しに入り込みやすくていいものだと思いました。 本の内容は、両親が沖縄出身で、本人は神戸で生まれ育ったという小学生の女の子を通して、沖縄出身者に対する差別や偏見、沖縄戦の悲惨さなどが描かれています。 物語を読んでて 「こんな大人びた小学生おらんだろっ!」 と突っ込みたくなる箇所が多数ありましたが、「沖縄」や「人権」に関して考えるには大変いい本だと思いました。 話しの中に 「沖縄の人は、沖縄戦で人には話せないほど悲しい辛い体験をしている。だからこそ人に優しくできる。」 と言うような内容が書かれていました。 特に、お話のクライマックスでの「ろくさん」の長い台詞のシーンは、幼い子供を持つ人間だけでなく、普通の心を持つ人間なら誰しも、涙無しでは読めないでしょう。 このシーンを読むだけでも十分価値のある本だと思います。 -------------------------------------------- 私が読んだ「灰谷健次郎」さんの3冊の本から読みとれる共通のキーワードは 「反戦」「差別」「人権」「弱者の視点」 という感じです。 現代の感覚から言うと少し 「古い」「臭い」「ダサイ」 という感じが否めませんが、一度は眼を通しておくべきだと思います。 ○「ナツコ 沖縄密貿易の女王」 沖縄勤務中の時、会社の上司に 「この本、読みやすくておもしろいぞ。糸満の本屋に入ると、この本ばっかり売ってるぞ。」 と言って渡されたのが 「ナツコ 沖縄密貿易の女王」 と言う本でした。(ちなみに、東京の本屋では見たことないです) この本は、戦後の混乱期に、沖縄の糸満を中心に、与那国、石垣、那覇などから、本土はもちろん、台湾、中国、韓国、フィリピンなどと密貿易をして、荒稼ぎをしていた「ナツコ」という実在していた女の人のお話です。 知っている地名がたくさん出てきますし、普段仕事で接していた糸満人(イトマンチュー)ですとか、糸満ハーレーに出ていた海人(ウミンチュー)達には、この様な歴史や習慣や気質があるのかぁ、と改ためて勉強になりました。 ちなみに、仕事を小一時間ほどさぼって「糸満ハーレー」を見に行ったことがあるんですけど、かなり面白かったですよ。やっぱ勝負形式のお祭りは盛り上がりますね。 半年間も沖縄の海辺で仕事をしていますと、何度も時化(しけ)た海を見る機会がありました。 それが、この「時化」の時の海の荒れ方が、もの凄いんですよ。 その凄い「時化」にも係わらず、天気予報もない時代に50馬力程度の船に乗って、本当に命がけで海に出る人達の凄さが、この本のいたるところに表現されていました。 それでも、やっぱり密輸の途中で遭難して死ぬ人がたくさんいたみたいですね。 漁師がサメを捕って腹を割いたら、胃から知ってる人の死体が出てきた。 「なんだ、長いこと帰ってこないと思ったら、あの船は遭難してたのか。」 というようなこともあったみたいです。 それと、この密輸というのが相当儲かったみたいです。 家でお金を置いておく場所がないので、布団のシーツ一杯にお金をいれていたり、船員の給料袋も今で言うゴミ袋くらいの大きさの袋に札束を入れて渡したり、札を数えるのが面倒なので、秤(はかり)で札束の重さを測って、だいたいこのくらいといってお金を払っていたみたいです。 戦後の物の無い時代に、今でいう何億円と言うお金が平気で動いていたみたいです。凄いですね。 ○余談です 実は、重松清の本を一番たくさん読みました。個人的にはこっちのほうが好きです。 それはまた次回書きますね。じゃ。 |
メール coil_oct14th@yahoo.co.jp |
ニュースのトップへ |
Oct.14thのトップへ